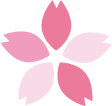9月19日(木)第11回復職支援研修を開催しました。

午前「摂食嚥下障害の看護」、午後「口腔ケア」:
バージニア・ヘンダーソンは「看護の基本となるもの」の中に、「患者の口腔内の状態は看護ケアの質を最もよく表すものの一つである」という一節を残されています。本日の研修は、口腔に重点をおいた研修を企画しました。
午前は、奈良県総合医療センターから摂食嚥下障害看護認定看護師を講師に招き、講義をしていただきました。講義の内容は、摂食嚥下の5期モデル(先行期・準備期・口腔期・咽頭期・食道期)、誤嚥や摂食嚥下障害をきたす疾患、嚥下機能が低下する薬剤、嚥下評価方法、口腔ケアについて150分の講義では足りないくらいの盛沢山の内容でした。実技は、2人ペアになり、摂食嚥下スクリーンテスト(反復唾液飲みテスト・改定水飲みテスト)を体験しました。講師は、「患者さんと関わる時は、口腔ケアにはじまり口腔ケアで終わると思ってほしいです。」と話されました。受講生は「自分が考えていたより嚥下というものが奥深くて、すごく勉強になりました。」「食事中の患者さんの視野を意識した介助を今後行いたいと思いました。」「働いていたときは根拠なく食事の姿勢を整えていたが、両脇の下に枕をいれる意味など間違っていたことに気付きました。」等の感想をいただきました。
午後は、奈良県歯科医師会から歯科医師と歯科衛生士を講師に招き、講義をしていただきました。歯科医師は、高齢者の口腔内の特徴、唾液の働き、摂食嚥下の機能、認知症を持つ高齢者の口腔ケア、オーラルフレイルについて、歯科衛生士は、口腔ケアの手順についての講義と、左半身麻痺のモデル人形に、臥床状態で口腔ケアを実施するデモンストレーションをされました。受講生は「健康は口からということがよくわかりました。」「歯科衛生士さんによる口腔ケアをデモで見させて頂きとても勉強になりました。テキストではわかりにくい事も直に見れたので参考になりました。」「明日から現場で使える事ばかりでとても良かったです。」等の感想をいただきました。受講生は、デモンストレーションを見ながら、懸命にメモをされ、今後の仕事に活用しようと前向きに取り組まれていました。
高齢化社会が進み、医療・介護をする上で摂食嚥下の知識は重要で、特に嚥下の奥深さを知ることができました。本日一日の研修を通して、口腔ケアの重要さについて改めて考える機会になりました。(奈良県ナースセンター)