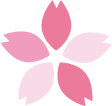
教育計画
Education Program
教育計画
教育理念
個々の看護職が専門職業人として、どんな時も人々の生命を尊重し人としての尊厳と人権を守り、 社会のニーズに対応した、安全・安心で信頼のおける医療・看護を提供するために、それぞれの 自己啓発とキャリア開発を支援し継続教育の推進に努める。
教育目的
- 社会のニーズに対応できる看護実践能力の向上を図る。
- 自らの責任において継続教育に参加し、専門職業人としての倫理的責任を養う。



教育目標
- 新しい知識や技術を習得し、看護実践能力を向上させる。
- 看護におけるマネジメント能力の開発を図る。
- 看護の実践に活用できる研究的視点や能力を養う。
- 専門職として感性を養い、安全で安心できる看護を提供するための能力を養う。
教育方針
公益社団法人奈良県看護協会は、公益社団法人日本看護協会との連携のもと、保健師、助産師、看護師及び准看護師が、教育と研鑽に根ざした専門性に基づき看護の質の向上を図るとともに、安心して働き続けられる環境づくりを推進し、あわせて人々のニーズに応える看護領域の開発・展開を図ることにより、人々の健康な生活の実現に寄与することを目的とし看護職がその役割や機能を最大限に発揮できるよう支援していきます。
(奈良県看護協会 定款2章3条)
看護職はあらゆる場において機能し、人々のためにその役割を発揮しています。
- 健やかに生まれ育つことへの支援
- 健康に暮らすことへの支援
- 緊急・重症な状態から回復することへの支援
- 住み慣れた地域へ戻ることへの支援
- 疾病・障がいとともに暮らすことへの支援
- 穏やかに死を迎えることへの支援
その役割を発揮するためには、継続教育が必要です。(日本看護協会看護の将来ビジョンより抜粋)
日本看護協会の従来の研修分類を基に奈良県の状況に合わせた8つに分類して研修を実施します。
研修の分類<これからの社会における看護の役割発揮を支援するための分類>
| 研修の分類 | 内容 |
|---|---|
| 1.「生活」と保健・医療・福祉をつなぐ質の高い看護の普及に向けた継続教育 |
|
| 2.ラダーと連動した継続教育 |
|
| 3.看護管理者が地域包括ケアシステムを推進するための力量形成に向けた継続教育 |
|
| 4.専門能力開発を支援する教育体制の充実に向けた継続教育 |
|
| 5.資格認定教育 |
|
| 6.学生教育を充実させるための継続教育 |
|
| 7.奈良県看護学会 | |
| 8.各委員会等と運動した交流会・研修 ※保健師・助産師・看護師・准看護師に向けた研修を含む | |
注) 今後は日本看護協会 看護職の生涯学習ガイドラインに基づいた研修の分類への変更を検討します。