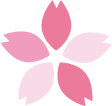9月3日(火)第9回復職支援研修を開催しました。

午前の「チームケア」は特別な実技を学ぶものではありませんが、看護を行う上でとても大切な技術の一つです。当協会専務理事に講師を依頼し、チーム医療の4要素(専門性志向・患者志向・職種構成志向・協働志向)、チーム医療の特徴と役割、医療接遇等について講義をしていただきました。講師は、「今日、研修に来られたことが素晴らしく、人と出会えたことで横の繋がりを大切にしてください。」と話されました。受講者は、「長く離れた医療職の現場での経験を思い出す良いきっかけになりました。私自身が看護職に戻りたいと漠然と思っていた原点を考える良い機会となりました。」「コミュニケーションがとれていたら、クレームが少なくなることが印象に残りました。」「患者様にも他職種の方々に対しても、普段からのコミュニケーションと信頼が大切だと改めて感じました。」「医療接遇について、自分が言われて嫌な気持ちになる言葉、言葉のキャッチボールができないような対応はしないよう気をつけ、患者の気持ちに寄り添えるよう医療接遇を行っていきます。とても丁寧でわかりやすい講義をありがとうございました。」等の感想をいただきました。
午後は、ハートランドしぎさん看護専門学校から講師を招き、看護記録の目的、取り扱い、法的位置づけ、注意点、電子化のメリットデメリット、構成要素、看護診断、看護計画、評価等について講義をしていただきました。受講生からは、「看護は好きだけど、記録が苦手です。」という声が多く聞かれます。しかし、看護記録は看護実践するうえで非常に重要です。講師は、「患者さんは日々変化していく存在です。患者さんから得た情報を看護過程にいかしていくことで、患者さんに適切な看護援助を提供していくことができます。結果として、それは患者さんの健康回復につながっていくのです。」と話されました。受講者は、「病院勤務時代に記録委員会に入っていて、憶測で書かないようにすることなど、病棟内で指導し、自分でもいろいろ気をつけていたのを思い出しました。看護診断など、久しぶりに復習出来て、すごく良かったです。論理的で分かりやすい講義でした。」「電子カルテを使用するようになり、電子カルテにあわせた看護問題になっていたなと反省しました。」「忘れている部分でもあり、技術では補えない部分でもあるので、講義を受けてとてもよかったです。」等の感想をいただきました。
電子カルテの導入により、業務改善につながっている一方で、情報を容易に持ち出せる危険性や、患者の個別性がなくなる等のデメリットがあることも学びました。本日は演習の多い講義でしたが、皆様熱心に受講されていたのが印象的でした。(奈良県ナースセンター)